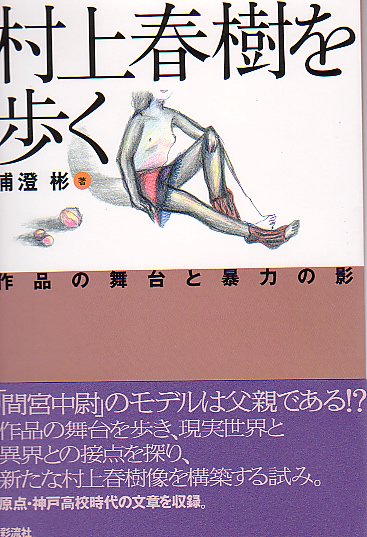『直子の井戸を探して〜フィールドワーク・村上春樹』
第1章『阪神間』
(3)
村上春樹の初期三部作に描かれた芦屋や神戸の街は、奇妙につくりものめいてみえる。村上の描く阪神間には、何かが欠落している。それは、村上が意識的に、また無意識的に省いた部分である。それがそのまま村上作品の長所にもなり、短所にもなっている。
大切な何かを欠落させたままであるということが、作品として顕著に現われてるのは、『風の歌を聴け』である。
「今、僕は語ろうと思う」と主人公の「僕」は宣言していながら、しかし、肝心のところはついに語られることなく終わってしまうのである。そういうところに、村上春樹の抱く深いトラウマが感じられてならない。
今回の『辺境・近境』における村上の阪神間散歩でも、そのトラウマは感じ取れる。それはもちろん父への屈折した思いであり、さらに暴力への強いこだわりである。村上春樹にとっての阪神間とは、決して美しいだけの風景ではありえない。
村上の、怯えともいうべき暴力への怖れを助長しているのは、村上の持つ予言者としての資質である。そもそも、今回村上が歩いた阪神間は、大震災によって破壊され、変わり果てた姿をみせているのだが、村上にとって、故郷の変貌を目の当たりにするのは、これが初めてではない。
村上が幼い頃を過ごした阪神間は、戦後徐々に変わりつつあったとはいえ、戦前からの伝統ある文化をしっかりと保持して、古き良き時代を髣髴とさせる場所だった。昔ながらのお屋敷もあり、浜辺では海水浴ができるような土地だった。ところが、村上が大学生になって東京へ去ったあと、開発によって浜は埋め立てられ、巨大なマンション街が出現し、古いお屋敷町も新興住宅地へと変わっていった。そういう故郷喪失の体験について、村上は恨みをこめるかのように描いている。
※引用(『羊をめぐる冒険』より)
《新しいジェイズ・バーの西側と南側には大きな窓があって、そこから山なみと、かつて海であった場所が見渡せた。海は何年か前にすっかり埋めたてられ、そのあとには墓石のような高層ビルがぎっしりと建ち並んでいた。》
※写真は著者撮影。新・ジェイズバーのモデルと思われる芦屋川沿いのテナントビル

※引用(村上春樹『カンガルー日和』より「5月の海岸線」)
《高層住宅の群れはどこまでも続いていた。まるで巨大な火葬場のようだ。人の姿はない。生活の匂いもない。
(中略)
僕は預言する。君たちは崩れ去るだろう、と。何年先か、何十年先か、何百年先か、僕にはわからない。でも、君たちはいつか確実に崩れ去る。山を崩し、海を埋め、井戸を埋め、死者の魂の上に君たちが打ち建てたものはいったい何だ? コンクリートと雑草と火葬場の煙突、それだけじゃないか。》
※写真は著者撮影。「墓石のような」と村上が書いたマンション群(現在は芦屋市にある公団住宅・芦屋浜シーサイドタウン)

ここに語られていることが、まさか予言となって本当に実現しかけるなどとは、村上自身思いもしなかったであろう。だが、予言は半ば的中した。阪神大震災によって、阪神間の埋立地のマンション群は「崩れ去り」かけた。まるで「火葬場」のように焼けそうになり、あやうく本当に「墓石」と化すところだった。
また、もう一つ予言がある。それは地下鉄サリン事件である。これについては、村上自らが語っている。
※引用(村上春樹『アンダーグラウンド』より)
《『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』には東京の地下の闇に生息する「やみくろ」という生き物(もちろん私が思いついた架空の生き物だ)が登場する。
(中略)
主人公の「私」は事情があってその地下の神話的世界に潜入し、「やみくろ」のぞっとするような追跡をかわしながら、不気味な深い闇を抜けて、地下鉄銀座線の構内から無事に青山一丁目に脱出する。
(中略)
地下鉄サリン事件のニュースを耳にしたとき、私は否応なくこの「やみくろ」のことを思い出してしまった。自分が地下鉄の窓の外に見たように感じた「やみくろ」のうす暗い影のことが脳裏にふと浮かんだ。きわめて個人的な恐怖(あるいは妄想)のレベルでいえば、この地下鉄サリン事件が投げかける後味の悪い黒い影は、東京のアンダーグラウンドの闇をとおして、私が自分で作り出した「やみくろ」という生き物(それはもちろん私の意識の目が見出すものだ)とつながっているように感じられる。》
このように、村上春樹の暴力を予見する感覚は異様に鋭いのである。その神経が、一見のどかな風景の中を歩いていても、村上を過度に怖れさせるのであろう。だから、地下鉄サリン事件もさることながら、阪神大震災による故郷の崩壊は、村上にとって想像を絶するショックだったのではなかろうか。その衝撃の大きさが、村上に過剰なまでの慎重さを強いているのかもしれない。また、一見奇妙な反応を震災に対してみせているのもそのせいであろうか。
※引用(村上春樹『村上朝日堂はいかにして鍛えられたか』より)
《テレビのニュースで、僕が通っていたその中学校を二度ばかり目にすることになった。一度は阪神大震災で亡くなった人々の遺体が校庭に並べられているところで、あと一度はテントの並んだ校庭で行われる震災直後の卒業式の光景だった。
(中略)
でも僕の頭にまず浮かんだのは、震災の犠牲者に対する同情の念よりは「ああ、俺はここでずいぶん教師に殴られたんだ」という息苦しい、にがい思いだった。もちろん地震の犠牲者の方々のことは心から気の毒だと思った。その人々の負った苦しみに比べたら、教師に殴られる痛みくらい無に等しい。でもそれにもかかわらず、あらゆる理屈や比較を超えて、僕はまだ自分の肉体と心に残っている傷の痛みを、まず最初にはっと思い出した。》
これはまた、奇妙な印象をうける文である。これでは、不謹慎だとあらぬ誤解をまねきかねない。それでも村上はこう書いた。それは、そうとしか表現できない心の傷の深さを暗示しているのであろう。つまり、書いてある体罰について額面通り受け取ることは、うかつにはできないということである。
むしろ、震災によって村上が受けた故郷喪失という心の傷の深さが、それを真正面から語ることを避けさせたと思えるのである。『風の歌を聴け』の場合と同じように、村上にまわりくどい表現を強いている。本当のところ、『辺境・近境』における阪神間散歩は、正面から故郷喪失に立ち向かおうという試みだったのかもしれない。だが、その試みはまたも挫折した。
村上春樹は、デビュー作以来、常に自分の心の傷を真正面から描こうとしていながら、どうしても視線をそらせてしまう。
『風の歌を聴け』の語り手が、「今、僕は語ろうと思う」と宣言しながら、ついに本当のところを正面きって語れなかったところが始まりである。
今度こそはと期待させた『ノルウェイの森』も、心の傷を真正面から描いているようにみえて、実は心の表面を奇妙に上滑りし続けるままに終わっている。
どうしてもトラウマと正面から向き合うことができないほど、村上の心の傷は深いのであろう。暴力へのこだわりを表現するために、震災ではなく地下鉄サリン事件を選んでしまうというところにも、その傾向が現われている
村上春樹にとっての暴力体験の原点は、イアン・ブルマのインタビューにあったように、早稲田での全共闘体験であるらしい。そのあたりをもう少し掘り下げてみるには、『ノルウェイの森』を調べる必要がある。
村上自身と共にあらためて阪神間を歩くことで、村上春樹の父への屈折した思いがいかに作品に反映されているかということ、そして暴力へのこだわりについて考えることができた。この暴力の問題をさらに考えてみるために、次は『ノルウェイの森』の作品舞台を歩いてみることにしたい。
(この稿、ここまで)

※前段まで
『直子の井戸を探して 〜 フィールドワーク村上春樹』浦澄彬 著
第1章『阪神間』(1)
https://doiyutaka.hatenadiary.org/entry/2024/10/17/182510
(2)その1
https://doiyutaka.hatenadiary.org/entry/2024/10/18/233908
(2)その2
https://doiyutaka.hatenadiary.org/entry/2024/10/20/163403
※本著作の続きを、このブログで連載継続するかどうか、まだ未定です。
1998年、小説『パブロのいる店で』(澪標)刊行。
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784944164202
2000年、村上春樹論の連載で関西文学選奨奨励賞受賞。
同年、評論『村上春樹を歩く』(彩流社)刊行。
https://www.sairyusha.co.jp/book/b10017327.html
2023年、『村上春樹の猿〜獣と嫉妬と謎の死の系譜』(電子版)刊行。
2024年、新刊発売予定
※Amazon 著者ページ
https://www.amazon.com/author/beunique